深さ100kmほどの地中でマグマが形成される = 海溝のすぐ近くではマグマにならない
マグマは比重が軽いため、割れ目があると上昇。地下10㎞あたりにマグマだまりをつくる。
→ さらに割れ目があるとそこからマグマが噴出。これを噴火という。
海溝から一定距離の大陸プレート上に火山が存在する。その火山帯の海溝側の境界のこと。
火山は海溝のすぐそばではなく、海溝から一定距離
離れたところに生成される。
ということは、海溝‐山地‐火山‐縁海‐大陸というように並ぶことが多いということ。
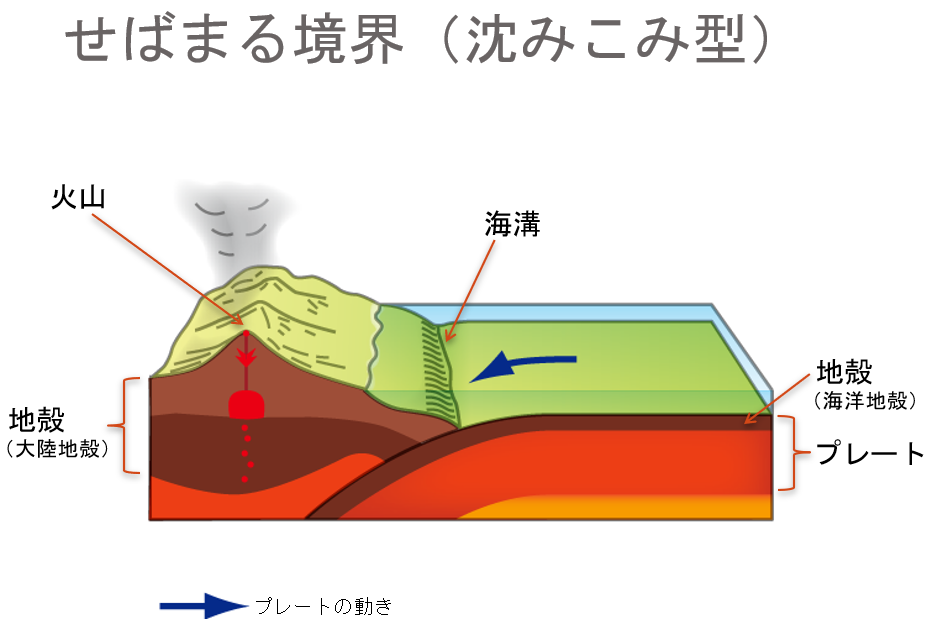
構造線
西縁が糸魚川~静岡構造線
北側の内帯は丘陵・高原・小規模の山地が分布。比較的低くてなだらか
南側の外帯は標高が比較的高く、V字谷が刻まれた山地・山脈が連なっている
日本の山野河川
- 山地
日本の国土の60%が山地
- 新期造山帯のため、急峻な山地・山脈が多く、山麓には扇状地が発達
- 平野
日本は山と雨が多いため、土砂が下流へ運ばれて
→ 谷底平野・扇状地・三角州が形成される
- 河川
勾配が急で長さが短い
- 氷河地形
約2万年前の氷河期には、日本にも山岳氷河が今以上に発達していた。
例えば、北海道の日高山脈や日本アルプス(飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)など。
現在は飛騨山脈に少しだけ見られる。
デレーケ
デレーケ(農林水産省HP)
237
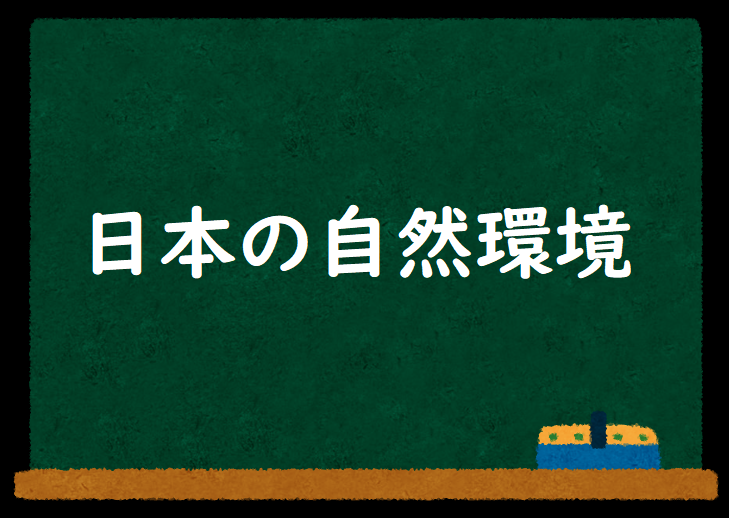
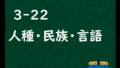

コメント