大気の循環
(1 )
気温が高く、上昇気流が発生
(2 )
熱帯低圧帯からの大気循環により下降気流が発生
(3 )=極偏東風帯
亜熱帯高圧帯からの大気循環により上昇気流が発生
※ 上空では成層圏が大気に蓋をしているため、上昇気流は宇宙に飛び出すことはない。よって、大気の循環がおこる。これによって、地球の熱エネルギーは均衡が保たれる。
※ 地表面ではコリオリの力により北半球では右、南半球では左に風の進行方向がずれる。これによって、(4 )=偏東風、(5 )、(6 )など恒常風がおこる。
※ 偏西風は上空10㎞付近で最も強くなり、これを(7 )とよぶ。ジェット気流は南北の熱エネルギーに差があると蛇行する。これを偏西風波動とよぶ。
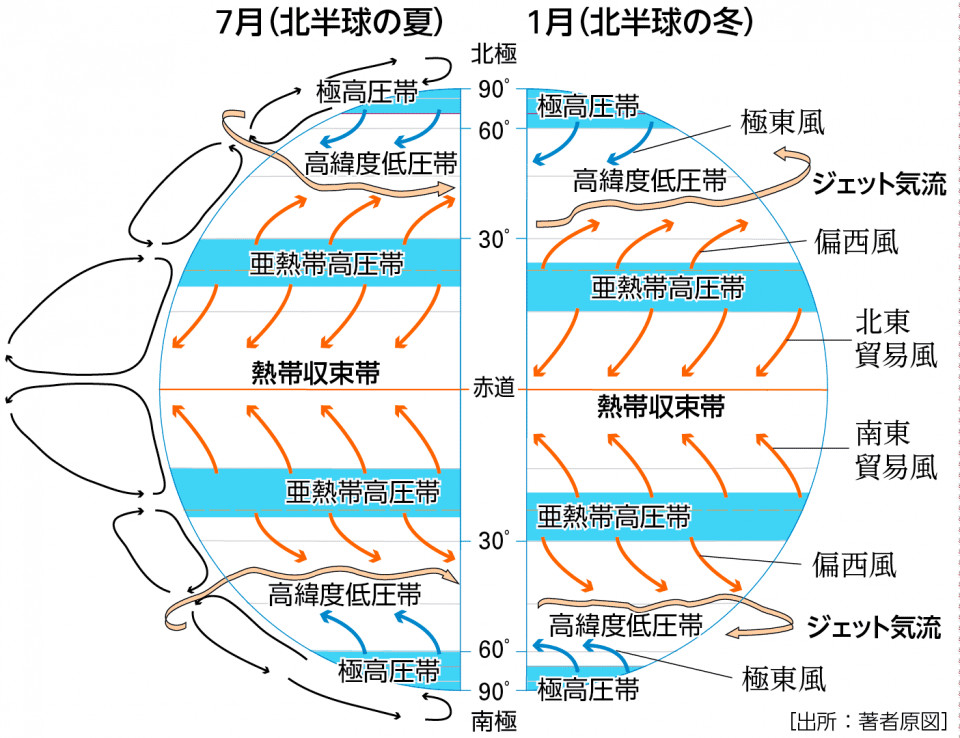
モンスーン(季節風)
(8 )… 季節によって向きが変わる風。大陸の東岸で発達しやすい風。
東アジア・東南アジア・南アジアでとくに発達
ユーラシア大陸西岸は西側が海 = 年較差が小さい
よって、吹き込んでくる偏西風の温度差も小さい
一方、大陸東岸は西側が内陸部 = 年較差が大きい。
よって、吹き込んでくる偏西風の温度差も大きい。
さらに、大陸との摩擦により偏西風自体も弱くなる

結果、大陸東部では陸地部分の夏と冬の温度差が大きくなり、気圧が夏と冬で逆転
→ 風は高気圧から低気圧に吹き込むので、季節によって風向きが変わる
よって、
夏は海洋から陸地へ、冬は陸地から海洋へ風が吹く(モンスーン)
東アジア(日本など)
夏に(9 )、冬に(10 )が吹く
南アジア
夏に(11 )、冬に(12 )が吹く
この地域を(13 )といい、世界のコメの生産の90%を産出。夏に降水量が多く、多雨である。
局地風
地球規模ではなく、局地的に起こる自然現象の一つ。その地方だけに存在する風を局地風(地方風)という
① (14 )
フランス南部のサントラル高地からローヌ川に沿って地中海に吹き込む寒冷乾燥の風。イタリアではマエストラーレとよぶ。
② (15 )
アルプス山脈の北側に吹き下ろす、高温乾燥な南風
※ 同じ現象が他所で起こった場合、(15 )現象という名称で一般化している
③ (16 )
ディナルアルプス山脈からアドリア海に向かって吹き下ろす、寒冷乾燥の風
④ (17 )
カスピ海北部に吹く、高温乾燥の東寄りの風
⑤ (18 )
サハラ砂漠から地中海を超えてイタリア半島南部に吹き込む、砂嵐を伴った高温湿潤の南風
⑥ (19 )
11~3月にサハラ砂漠からギニア湾岸に吹き込む、高温乾燥の貿易風
その他に、ブリザード(アメリカ北部の吹雪を伴う突風)、チヌーク(ロッキー山脈から東側に吹き下ろす熱風)、が有名。日本では「〇〇おろし」や「やませ」が有名

熱帯低気圧
熱帯低気圧熱帯の太陽上に発生する移動性低気圧
(20 )= 台風、北西太平洋
(21 )= 大西洋、北東太平洋
(22 )= インド洋、南太平洋
というように、場所によって名称が異なる。
※ 台風の名称
日本ではその年に発生したものを順番に番号をつけている。
そのほかにアジア全体で名称を順番に決めて、その名で呼ぶこともある。
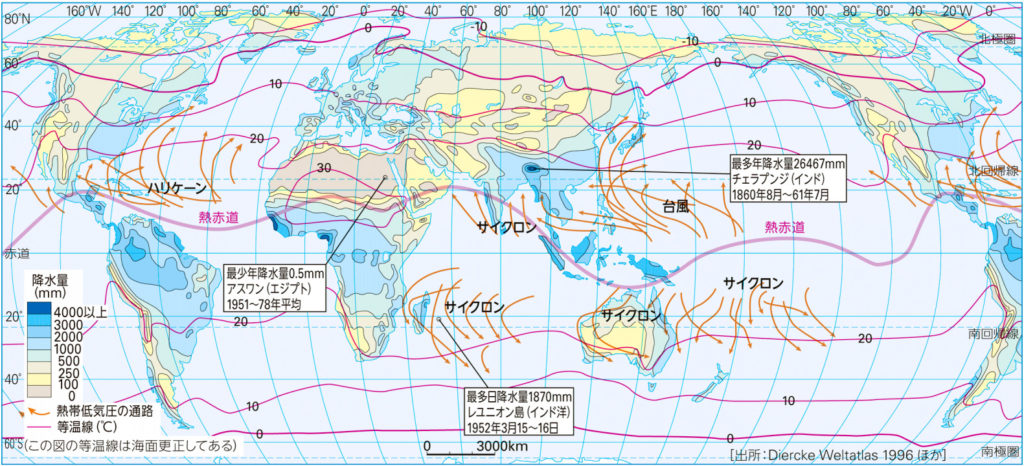



コメント