1. 風の流れ
→ 熱や水蒸気を運ぶ
もし、これがなかったら
これによって大気の大循環が起こる。
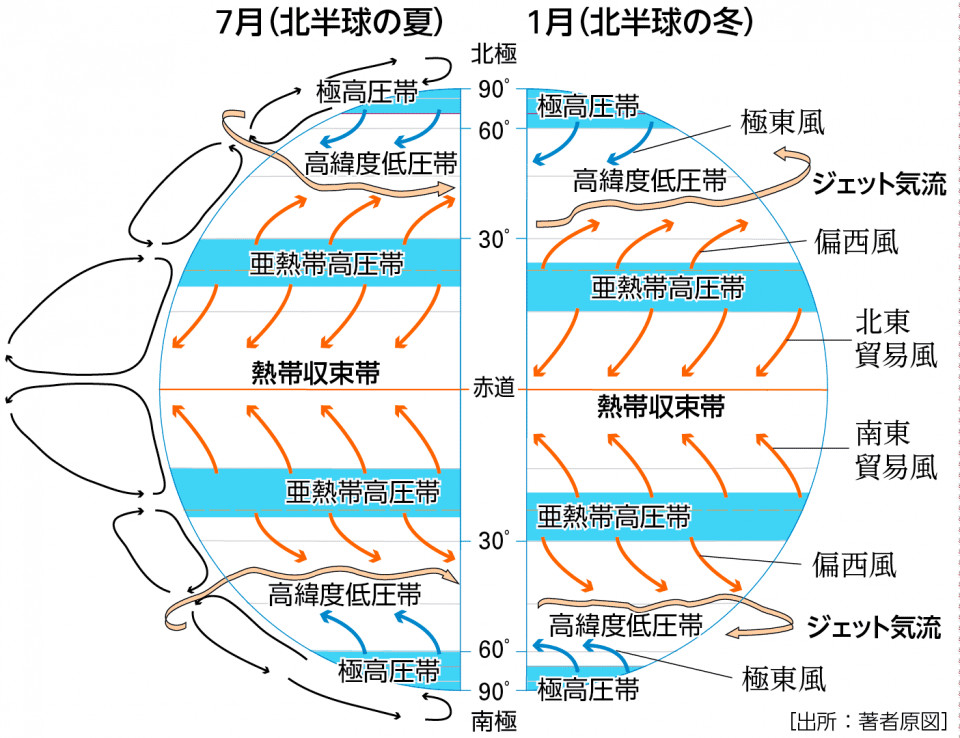
_CT703_fig_034-02_4c-424x1024.png)
2. 季節的な降水量の変化
(北半球の夏)
太陽は北回帰線付近を通る
→ 熱帯低圧帯は北回帰線付近に移動、大気の循環そのものが北にずれる
北極付近では(8 )となる。気温が上がるため、極高圧帯は小さくなる
この時、南極付近は(9 )となる。気温が下がるため、極高圧帯は大きくなる
(北半球の冬)
上記の反対のことが起こる
→ 季節によって降水量が違う地域ができる
3. 海洋と大陸の分布と風
暖かいところで上昇気流が起こる。したがって
陸地が温まるので、上昇気流が起こる。その結果、海洋から陸地に風がふく
陸地が冷めるので、下降気流が起こる。その結果、陸地から海洋に風がふく
4.海流
沖合に寒流が流れていると、上昇気流が起きづらいので降水量が少なくなる
→ 沿岸部に砂漠ができる
例)南アメリカ大陸のアタカマ砂漠、アフリカ大陸のナミブ砂漠
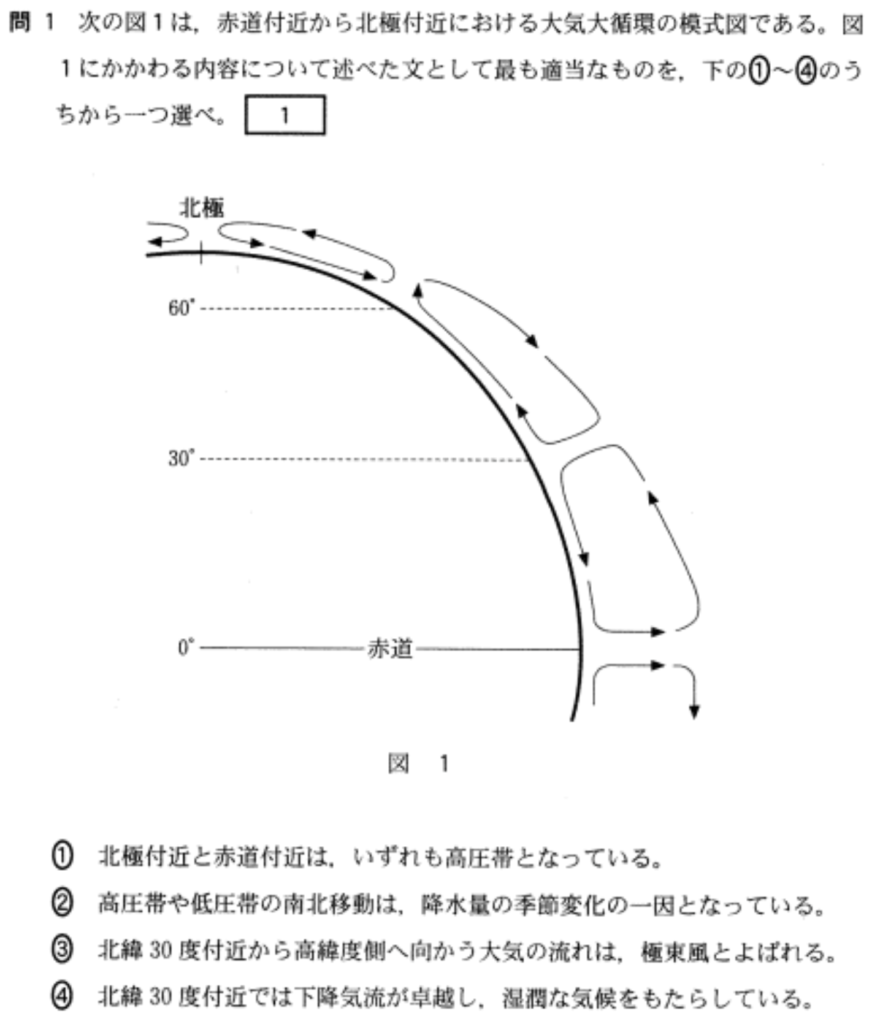

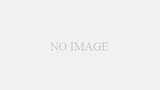
コメント