資源・エネルギーの生産
鉱産物・化石燃料は埋蔵量に限りがある、地球上に偏在
さらに、技術的に採ることができるか、採るためのコストに見合うかが問題になる
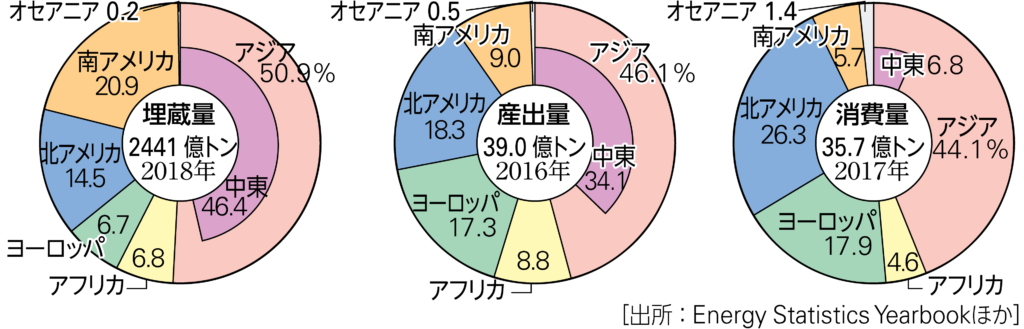
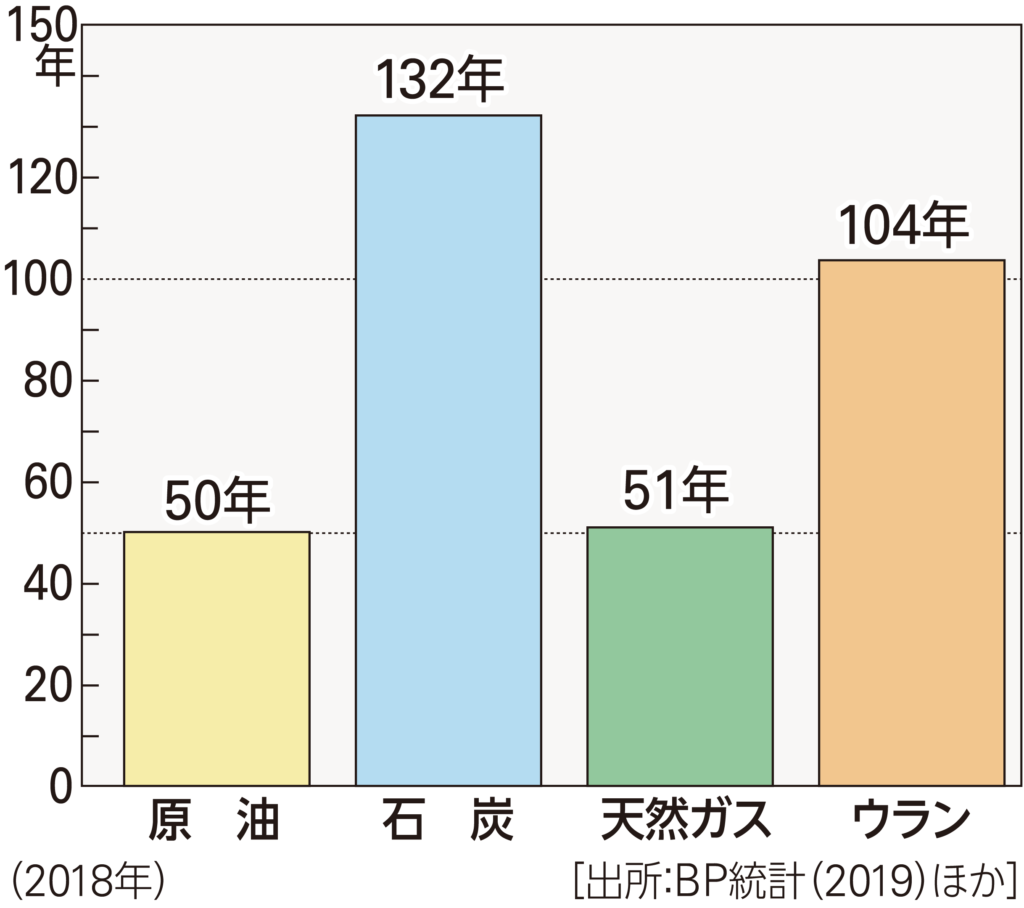
文明の発達に従って、人類はより多くの資源・エネルギーを必要とするようになった
→ エネルギーを獲得できるかによってその国が発展できるかが決まる
資源・エネルギーの消費
(1 )… 自然界に存在するそのままのエネルギー、石炭・石油など
左のグラフを見て、どのような国で多くなるのか考えてみよう

・ 中国はなぜ大きく違うのでしょうか?
・ サウジアラビアはなぜ大きく違うのでしょうか?
・ インドはなぜ急激に供給量が伸びているのでしょうか?
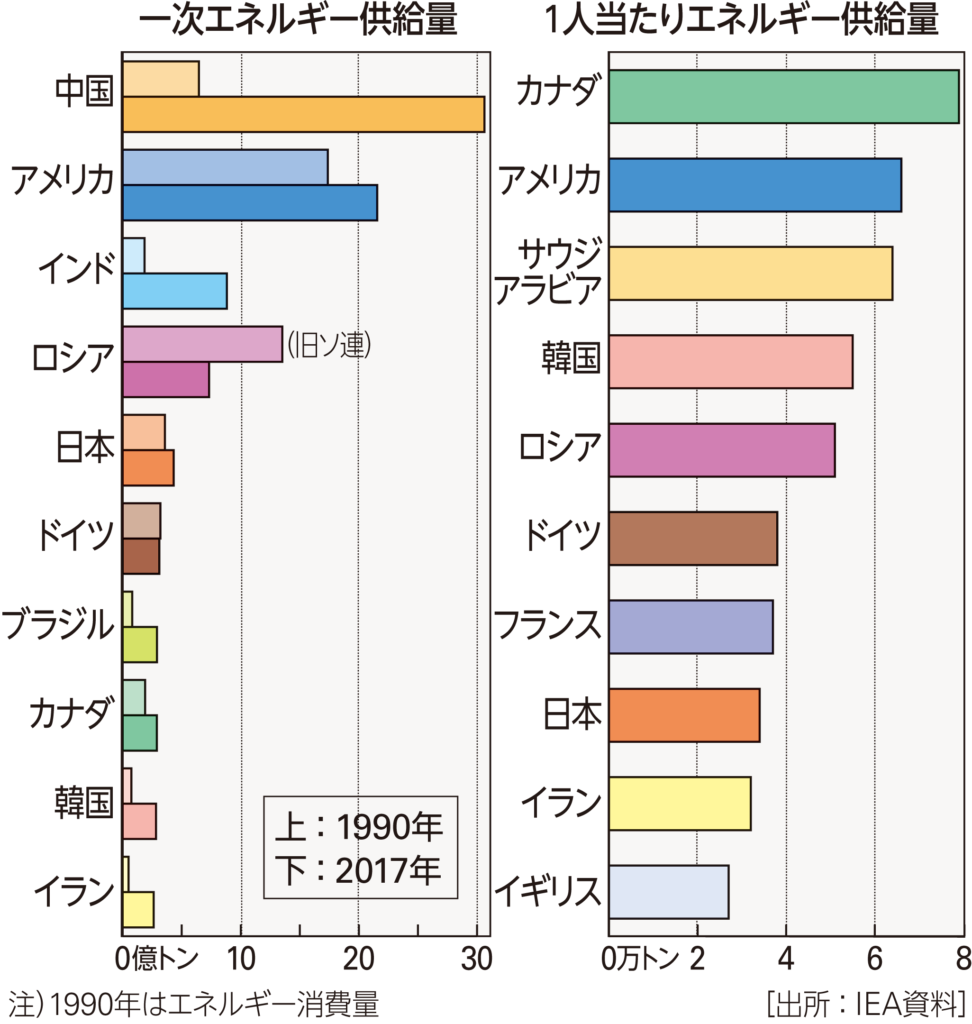
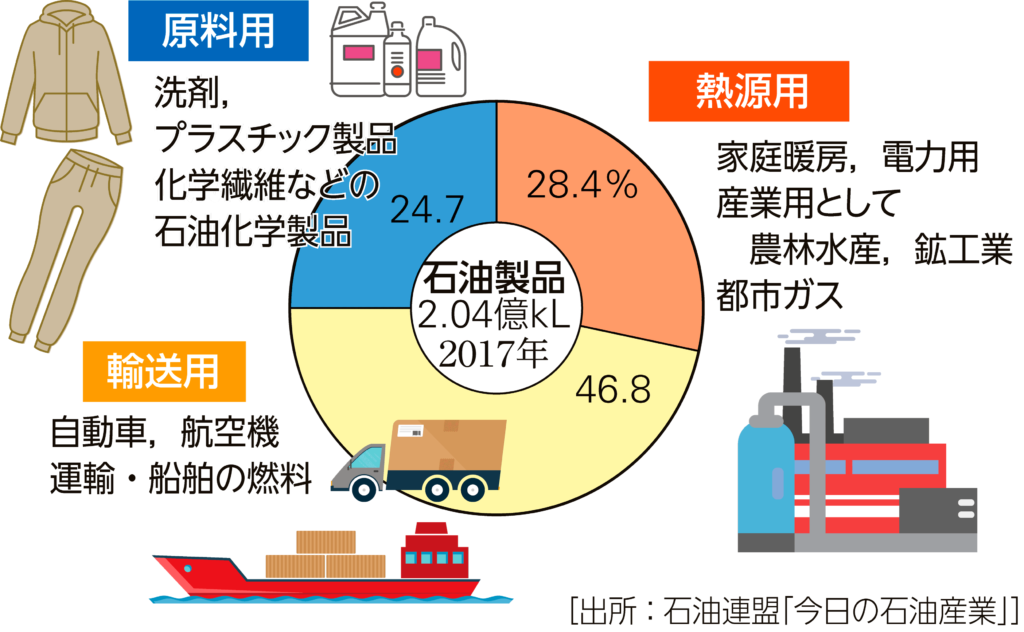
資源をめぐる対立
その背景には蒸気機関の改良があった … (4 )をエネルギーとして使用
20世紀 第二次産業革命 … (5 )の使用が中心となる、重化学工業化
1960年代 エネルギー革命 … 主なエネルギーが(4 )から(6 )へ
以上の流れの中で先進国は化石燃料への依存を高めた
→ 資源を確保しようとする各国は対立を深める
- 資源を自国の発展に利用しようとする動き
1970年代 二度にわたる(8 )が発生 → 石油価格の高騰、経済の混乱
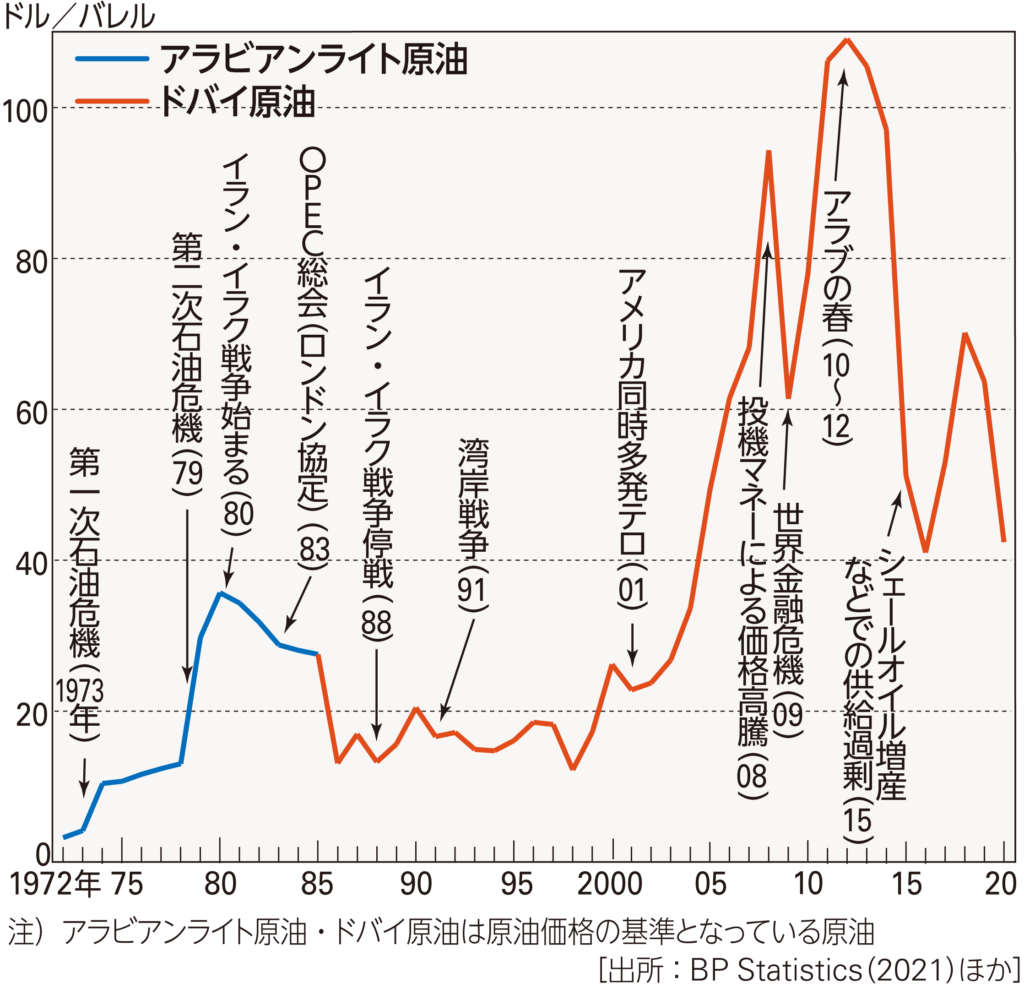
石油の備蓄が始まる、代替エネルギーの開発が始まる
2000年代
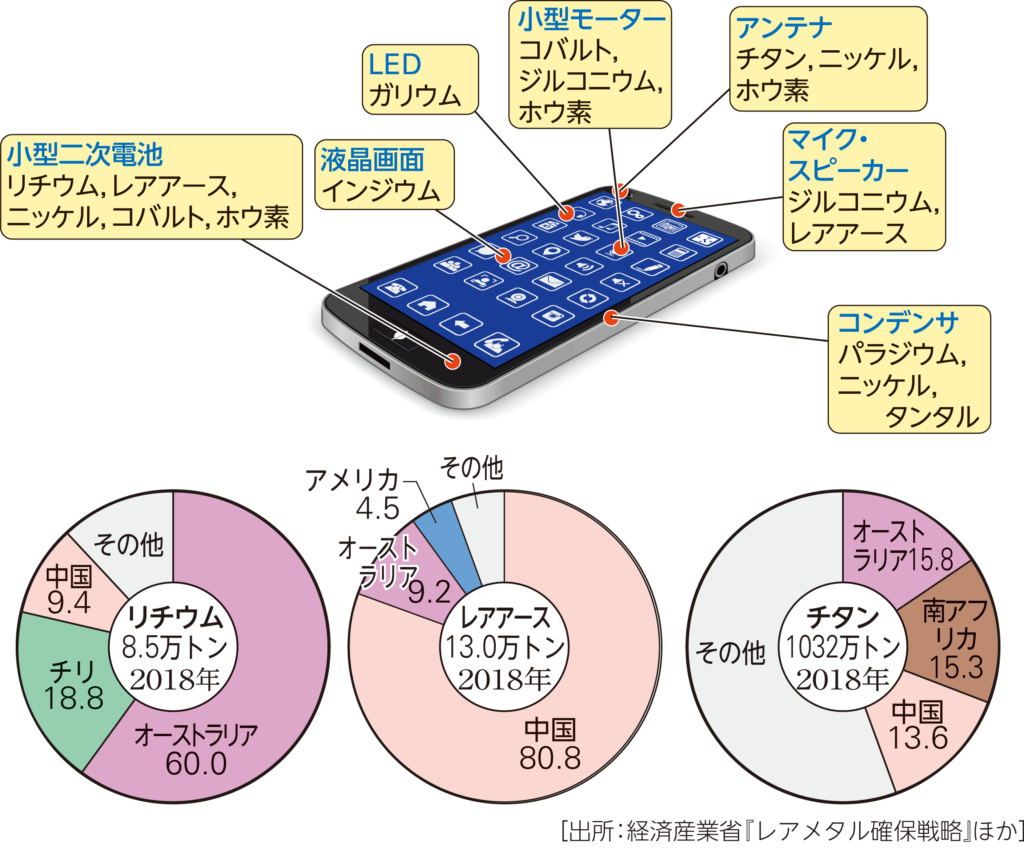
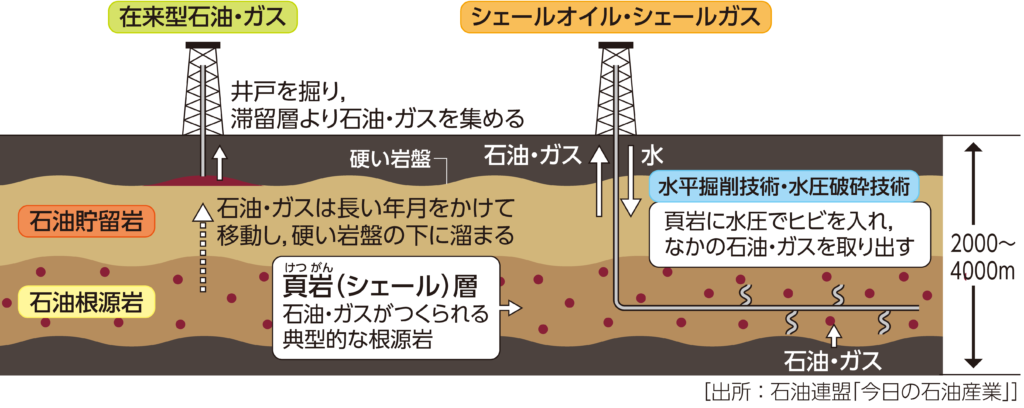
ウクライナ危機
ロシアがウクライナに侵攻。ロシアに対する制裁を行う諸国にロシアは資源を武器に対抗
世界でエネルギー価格が上昇

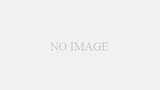
コメント