
24年の早稲田大学教育学部の地理の問題です。
先日行われたばかりのものですが、ちょうど今学習している範囲なので紹介します。
「正解」の後ろの部分をタップすると答えが見られます。
次の文章1と2は、日本国内で発生する自然災害のうち、風水害と地の特徴および、それぞれの災害の具体例について述べたものである。文章をよく読み、以下の問いに答えよ。
1.近年、前の器や台風の通通に伴う①集中豪雨が頻繁に発生している。大量の水が河用に流入すると、河川の水が堤防を越えたり、堤防が決壊したりして水害が起こる。
令和元年東日本台風(2019年10月の台風19号)の通過では、 関東・甲信越地方や東北地方などで記録的な大雨となり、各地で大規模な水容が発生した。たとえば、長野県を流れ る( a )川の決壊で北陸新幹線の車両基地が浸水したり、埼玉県を流れる( b )川の支流の決壊では、老人福祉施設が水没したりするなどの甚大な被害が出た。
いっぽう。おもに都市部では河川の水位が上昇した時や、下水道などの排水能力を上回る雨が降った時に、②雨水が河川に排水されずにあふれ出して浸水する被害もみられる。③交差する鉄道や道路などの下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっているような道路や地下街では、冠水するリスクが極めて高い。
水害を軽減するための対策として、これまで河川にダムや提防を建設するなどの方法がとられてきたが、近年では。 このような人工的な構造物に頼る方法だけでなく、河川の( E )全体を通じた総合的な治水へと、水害対策の考え方が見直されつつある。
2.日本列島は( c )つのプレート境界が集まる変動帯に位置している。プレートの運動によって、日本列島には圧縮する力がかかり続けており、自身が頻繁に発生する。地震には、プレート内部の断層がずれ動くことによって発生するタイプの地震と、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所である( F )やトラフで歪みが解放されることによって発生する( F )型の地震とがある。 断層のうち、最近数十万年間に繰り返し活動し、今後も活動する可能性が高いものを( G )という。たとえば ( G )型の地震の例としては、1995年1月17日午前5時46分に発生した兵庫県南部地震がある。この地震は( H )を引き起こし、神戸市を中心に建物や高速道路が倒して、6千人を超える死者を出した。
いっぽう、( F )型の地震の例としては、2011年3月11日午後2時46分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード( d )の地震が挙げられる。この地震は東日本大災を引き起こし、関東地方から北海道にかけての広い範囲に津波が到達して、2万人を超える死者・行方不明者を出した。
問1 文中の空欄a~dに該当するものをそれぞれ選択肢のなかから一つ選びなさい。
a( 木曽 ・ 黒部 ・ 千曲 ・ 天竜 ) 正解 ●●●
b( 荒 ・ 鬼怒 ・ 相模 ・ 那珂 ) 正解 ●●●
c( 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ) 正解 ●●●
d( 6.0 ・ 7.0 ・ 8.0 ・ 9.0 ) 正解 ●●●
問2 下線部①に関して、集中豪雨をもたらす一因である「次々と発生する積乱雲が、数時間にわたってほほ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、強い降水を伴う雨域」を何というか。
正解 ●●●
問3 下線部②のような浸水被害を何というか。
正解 ●●●
問4 下線部③のような形状を示す道路を何というか。カタカナで答えなさい。
正解 ●●●
問5 文中の空欄Eには「降水が河川に流れ込む範囲」を意味する語が入る。この語を漢字で答えなさい。
正解 ●●●
問6 文中の空欄Fに該当する語を、答えなさい。
正解 ●●●
問7 文中の空欄Gに該当する語を、答えなさい。
正解 ●●●
問8 文中の空欄Hに該当する災害の名称を、答えなさい。
正解 ●●●
問9 下線部の地器の名称を、答えなさい。
正解 ●●●

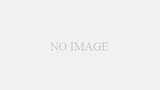
コメント