西南学院大学
次の文は,小地形に関するものである。これについて,問(1~3)に答えよ。
地形を作り変化させる力を営力という。そのうち,河川の流水をはじめ,風や雨,波,氷河などの風化・侵食・運搬・堆積作用を生み出す力を< ア >営力という。< ア >営力によって小地形が作られる。
山地を流れる河川の急流では,侵食・運搬作用が働き,川底が削られ,谷が深くなり,さらに周囲の斜面が山崩れや地滑りを起こしやすくなって, A 谷が作られる。また,海岸では,長期的には,海に注ぐ河川の作用や気候の変化などに伴う海面の高さの変動などの影響を受け,さまざまな海岸地形が作られる。
陸地との関係で海面が相対的に上昇すると陸地が海面下に没することになる。このような海岸は< イ >海岸という。また反対に,陸地との関係で相対的に海面が下降することによって,海底が海面上にあらわれる。このような海岸を< ウ >海岸という。
< イ >海岸の地形の例として, B 海岸が挙げられる。これは,山地や丘陵が海面下に没することで,小さな湾が連続したノコギリの歯のような形の海岸線をもつ地形である。 B 海岸は,志摩半島や( a )などでみられる。また,山地の大部分が海面下に没し,山頂や尾根だった部分が海上に散在する海域を C 海という。 C 海は,九十九島や( b )などでみられる。河口付近では,河口部分が海面下に没して,海水が入り込むとラッパ状の入り江になる場合がある。この地形は D とよばれる。セントローレンス川の河口や( c )川の河口でみることができる。
< ウ >海岸の地形の例としては,海食崖の下にある平坦面が< ウ >によって海面上にあらわれ,形成される< エ >が挙げられる。< エ >では階段状の地形がみられることもある。こうした< エ >は襟裳岬や( d )などにみられる。
海岸近くに形成されることが多いサンゴ礁について,その発達を,次のような3段階に分ける考え方がある。まず島々でサンゴ礁が陸地を縁どるように発達すると,< オ >礁ができる。< オ >礁は,例えばモーレア島や( e )などにみられる。< オ >礁が発達した後,島が没し始めると,海岸とサンゴ礁の間に礁湖ができる。この状態を堡礁という。さらに,島が完全に没するとサンゴ礁だけが残り, E 礁ができる。
問1 文中の(A~E)に最も適当な地形名を記入せよ。
問2 文中の( )(a~e)に最も適当な地名を,それぞれの地名群(11~13)から1つ選んで,その番号を記入せよ。
( a )
11 若狭湾 12 大阪湾 13 陸奥湾
( b )
11 石狩湾 12 松島湾 13 富山湾
( c )
11 エルベ 12 ナイル 13 ガンジス
( d )
11 南鳥島 12 室戸岬 13 野付半島
( e )
11 利尻島 12 天売島 13 石垣島
問3 文中の< >(ア~オ)に最も適当な語を,次の(11~22)から1つ選んで,その番号を記入せよ。
11 内的 12 外的 13 沿岸流 14 沈水
15 ウバーレ 16 海岸段丘 17 離水 18 裾
19 岩石 20 ポリエ 21 浜堤 22 砂嘴
野付岬(GOOGLE MAPS)
どのように成立した地形かは復習しましょう。
エルベ川(ラベ川)河口のエスチュアリー
写真だとわかりずらいので地図にしました。加工部分がラッパ状に広がっています。
ガンジス川河口付近の三角州
メグナ川と表記されていますが、この少し上流でガンジス川と合流しています。河口付近に島がたくさんあります。これが三角州。

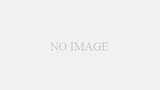
コメント