消費生活と商業
商品は生産者から消費者の元に届くまでに流通する。この流通機構を商業という。
このうち、身の回りにある店、「小売店」について学ぶ。

以下のお店の商圏はどのような範囲になるか考えてみましょう。
- 学校のそばのコンビニエンスストア
- あなたの家のそばのスーパーマーケット
- 秋葉原駅前のヨドバシカメラ
- 川崎の「Y’s ROAD」
- 神保町にある参考書専門古書店
商業の立地
商品には大きく分けて次の種類がある
(3 )… 購入頻度はそれほど高くない。あちこちで見比べて買うようなもの。
(4 )… 購入頻度は高い。習慣的に・生活上必要で買うもの。

では、上の3種類の分類に当てはまるのはどんなものか考えてみましょう。
そして、それをどのようなお店で買うのかを考えてみましょう。
その時、①〜⑤のお店を参考にしてみてください。
どのようなところに立地するか?
A ターミナル駅など人の多いところ
例えば、渋谷、新宿、池袋など。たくさんの人が行き交っている。
B 地元の駅のそば、住宅地の中の便利なところ。職場や学校のそば。
普段買い物に使う。
C 郊外の道路沿い
では、A,B,Cに行くときにどのような手段で行くのかを考えてみましょう。
次に、A ,B,Cに行くのはどのような時かを考えてみましょう。
インターネットによる変化
インターネットによる商品販売
専門店の場合(AMAZONなど)
基本的にインターネットのみで販売している。
宅配便と結びつき、家に居ながらにして購入できるので非常に便利
既存の店舗との組み合わせ
インターネットでも販売しているが、実際の店舗でも販売している
お店にとっては、商圏を無視できる(= 拡大する)、インターネットでの注文を機に実店舗に来てもらえる可能性があるなどのメリットがある。
時代による変化

現在、単位面積あたりの売り上げが多い順に並べてみよう
・ 百貨店(デパート)
・ スーパーマーケット
・ コンビニエンスストア

現在、商店街は非常に厳しい環境にあり、中には閉鎖に追い込まれるところもある。
なぜ厳しいのか考えてみましょう。
以上のことから、お年寄りは「フード・デザート」と呼ばれる問題が起こっている。これは、自家用車などの移動手段を持たないお年寄りが、栄養のある食品を安く買うことができなくなるという問題である。なぜそのようなことが起こるのか考えてみよう。

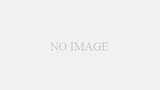
コメント